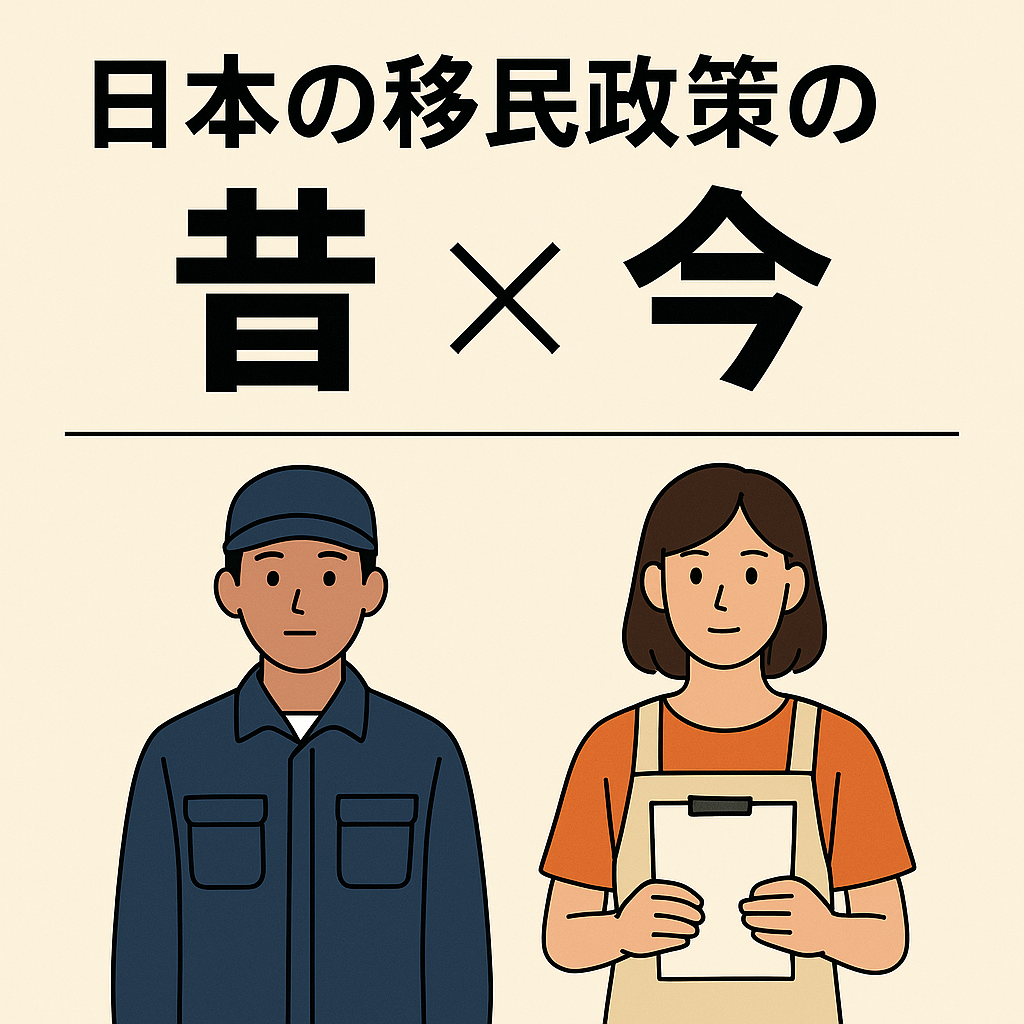少子高齢化と人口減少が急速に進む日本。
近年は外国人労働者や留学生の姿も身近になりましたが、「日本は移民を受け入れる国なのか?」と聞かれると、はっきり答えにくいところがあります。
本記事では、日本の移民政策の歴史と、2025年現在の最新動向をセットで解説します。
昔からの基本方針、バブル期以降の変化、そして現在の「特定技能」や技能実習の見直しまでを、ブログ向けに分かりやすくまとめました。
1. 日本の移民政策をざっくり一言でいうと?
日本の移民政策には、現在も「日本は移民国家にはならない」という建前があります。
そのため、カナダやオーストラリアのように「移民を前提とした永住受け入れ」の制度は整っておらず、 基本は
- 短期滞在(観光・ビジネス)
- 在留資格ごとの就労ビザ(専門職・技能職など)
- 留学・家族滞在
といった枠組みで外国人を受け入れています。その法律的な土台が、1951年制定・現在も改正を続ける出入国管理及び難民認定法です。
とはいえ現実には、2024年末時点で約377万人、2025年6月には約396万人と、外国人住民は急速に増加しており、総人口の約3%を占めるまでになっています。 政策上は「移民国家ではない」としつつも、実態としては外国人に強く支えられる社会へ変わりつつあるのが現在の日本です。
2. 戦前〜高度成長期:外国人は「統治対象」から「例外的存在」へ
2-1. 帝国時代:植民地出身者と出稼ぎ労働者
明治〜戦前の日本は、朝鮮や台湾などを植民地支配していた時代です。
多くの朝鮮半島出身者が本土に移り住み、鉱山・工場・建設現場などで働いていましたが、彼らは当時「日本臣民」とされた一方で、差別的な扱いを受けていました。
また、戦時中には中国や朝鮮から強制連行された労働者も多く、現在も補償や歴史認識をめぐる議論が続いています。 この時期の外国人政策は、現在の「移民政策」とは性質が異なり、帝国の拡大と戦争動員の文脈で捉える必要があります。
2-2. 戦後〜高度成長期:原則「移民を入れない」
敗戦後、在日コリアンや在日華人は日本国籍を失い、「外国人登録制度」の対象となりました。 1951年には現在につながる出入国管理令(のちの入管法)が制定され、入国管理と難民認定を一元的に扱う枠組みが整います。
高度経済成長期、日本は深刻な人手不足に直面しましたが、ヨーロッパ諸国のように積極的な外国人労働者の受け入れは行わず、国内の人手・長時間労働・機械化で乗り切る道を選びました。 この時期の基本スタンスは「移民の受け入れはしない」「難民認定も非常に限定的」という、いわゆる鎖国的な移民政策でした。
3. バブル崩壊後〜2000年代:「労働力不足」と矛盾する建前
3-1. 1990年入管法改正と日系人の受け入れ
1990年の入管法改正では、日系2世・3世を対象とした「定住者」在留資格が新設され、ブラジルやペルーなど南米から多くの日系人が工場労働などに従事するようになります。 これは事実上の外国人労働者受け入れ策でしたが、政府はあくまで「血縁のある人を受け入れているので移民政策ではない」と説明してきました。
3-2. 技能実習制度のスタート
1993年には、開発途上国への技術移転を名目とする技能実習制度が始まります。 しかし実際には、建設・農業・介護など人手不足の現場で安価な労働力として使われるケースが多く、長時間労働や暴力、賃金未払といった人権侵害が国内外から厳しく批判されてきました。
つまりこの時期の日本は、表向きは「単純労働の外国人は受け入れない」としながら、実際には技能実習生や留学生アルバイトなど、実質的な労働力としての外国人を増やしていくという矛盾を抱えていたのです。
3-3. 難民認定の厳しさ
日本は1981年に難民条約に加盟し、入管法に難民認定の規定を加えましたが、認定数は長年「世界でも最低レベル」と指摘されてきました。 2023年の入管法改正では、収容や送還をめぐるルールが見直されましたが、国際人権団体や弁護士会からは「保護より送還を優先している」との批判も続いています。
4. 現在の移民政策の柱:特定技能・技能実習見直し・高度人材
4-1. 「特定技能」制度の創設と拡大
2019年に導入されたのが、特定技能(Specified Skilled Worker:SSW)という新しい在留資格です。 18歳以上で一定の技能試験と日本語能力試験に合格した人を、介護・外食・宿泊・農業など人手不足の14分野で受け入れる仕組みで、在留期間の更新や家族帯同の可否などが定められています。
2024年の入管法改正と2025年の運用見直しでは、手続きの簡素化や受け入れ機関の管理強化、地方自治体との連携などが進められ、「人権を守りつつ安定的に受け入れる」方向へ制度改善が行われています。
4-2. 技能実習から「育成就労(仮称)」へ
旧来の技能実習制度については、低賃金・人権侵害などの問題が相次いだことから、政府の有識者会議が大幅な見直しを提言しました。 2024年には「外国人育成就労制度」の骨子がまとまり、2027年をめどに新制度へ全面移行する方針が示されています(ESD:Employment for Skill Development ビザとして運用予定)。
新制度では、労働者としての権利保護と技能向上を前面に出し、一定期間後には特定技能への移行をしやすくするなど、「人材育成から長期就労へのパス」を意識した設計が目指されています。
4-3. 高度人材・起業家の受け入れ
近年は、エンジニアや研究者、経営者などの高度人材向け在留資格も拡充されています。
ポイント制の「高度専門職ビザ」やスタートアップ向けの在留資格緩和などを通じて、ビジネス・投資・イノベーション分野の外国人を呼び込もうとする動きが強まっています。
5. 「今」の日本の移民政策が抱える課題
5-1. 人口減少と労働力不足は待ったなし
日本の労働力人口は今後も大きく減ると予測されており、2040年には1100万人以上の人手不足になるとの試算もあります。 その一方で、日本に住む外国人は2025年半ばで約395万人、外国人労働者は約200万人とされ、外国人なしでは回らない産業が急増しています。
5-2. 社会の不安と反移民感情
外国人住民が増える中で、治安や文化の変化、観光公害などへの不安から、反移民的な主張を掲げる政党の支持が伸びる動きも出ています。 2025年には、外国人をめぐる問題に対応するための新たな政府組織も発足し、「共生」と「秩序」の両立を掲げた議論が進んでいます。
5-3. 難民・庇護制度の見直し
紛争や迫害から逃れてきた人々に対する難民認定・在留特別許可のあり方は、今も大きな課題です。 2023年の入管法改正は、収容・送還の強化に比重が置かれているとして、難民支援団体から強い批判を受けました。 「労働力としての外国人」と「保護を必要とする難民」をどう位置づけるかは、日本の人権意識が問われるテーマと言えるでしょう。
6. 昔と今の移民政策を比較して見えてくるもの
6-1. かつて:門戸は狭く、例外的に受け入れるスタイル
- 戦後長く、「移民は受け入れない」「難民もごく一部のみ」という方針
- 例外として、在日コリアン・華人、日系人、技能実習生などを個別に受け入れ
- 制度よりも「現場まかせ」で、権利侵害や差別が問題化しやすかった
6-2. 今:建前は維持しつつ、事実上の受け入れ拡大へ
- 特定技能や高度専門職など、長期就労・定住を前提とした在留資格が拡大
- 技能実習の改革や新制度(育成就労・ESD)により、「労働者としての保護」を強調
- 外国人住民は約400万人、外国人労働者も増加し、社会のインフラを支える存在に
それでもなお、日本は欧米のように「移民を積極的に募集し、永住前提で受け入れる国家」とは言い難く、
「移民国家ではない」と言いながら、現実には移民に依存していくという独特のスタイルをとっています。
7. これからの日本の移民政策はどうなる?
今後の日本の移民政策は、次の3つのポイントをどうバランスさせるかにかかっています。
- ① 労働力確保:介護・建設・ITなど人手不足産業をどう支えるか
- ② 権利保護と共生:技能実習や特定技能の現場で、搾取を防ぎ生活を支える仕組みづくり
- ③ 社会の理解:偏見や不安を和らげ、多文化共生を当たり前にする教育・コミュニケーション
日本は長いあいだ「単一民族」「移民の少ない国」として語られてきましたが、 すでにコンビニ・介護施設・建設現場・IT企業など、身近なところで外国人と共に働き暮らす時代に入っています。
「昔はどうだったのか」「今何が変わってきているのか」を知ることは、
これからの日本社会をどのような形にしたいのかを考えるうえで、非常に大切な第一歩です。 ニュースの数字や制度改正の見出しだけでなく、その背景にある歴史と人びとの姿にも目を向けていきたいですね。